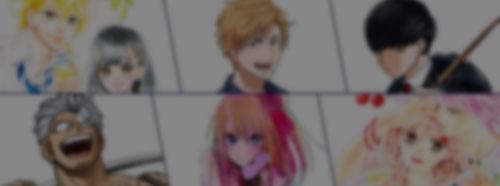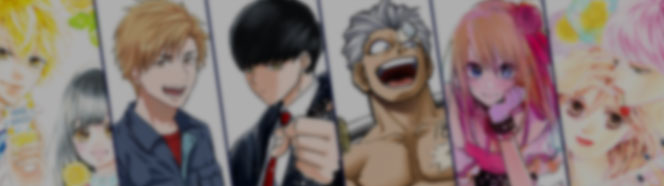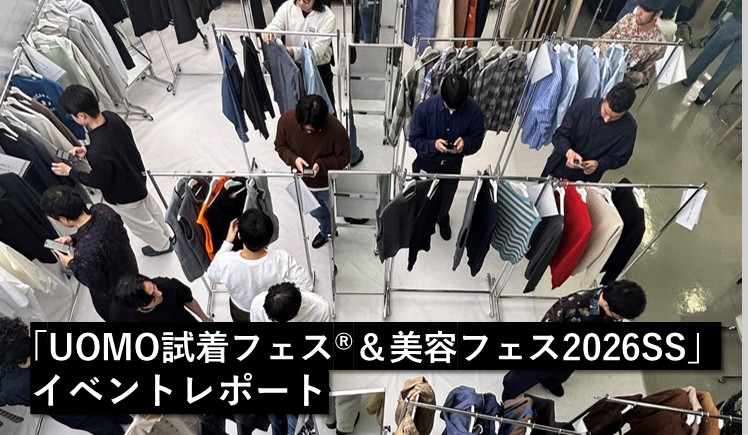「MORE JAPAN by SHUEISHA」特別企画【前編】
内閣官房 岸田里佳子審議官に聞く「地方創生」の現在地
集英社は2025年、雑誌『MORE』が立ち上げた地方創生プロジェクト「MORE JAPAN」を、今後は集英社のオールメディアで取り組む「MORE JAPAN by SHUEISHA」へ発展させ、より広く地方・地域創生の取り組みを推進していくことを宣言。そのプロジェクトチームをメディアビジネス部へ移管しました。
今回、元『MORE』編集長で「MORE JAPAN」発起人の中田貴子と、「MORE JAPAN by SHUEISHA」プロジェクトリーダーの清田恵美子が、内閣官房 地域未来戦略本部事務局の岸田里佳子審議官にインタビューを実施。地方・地域創生の現在地や、雑誌メディアだからこそできる取り組みについて、意見交換を行いました。前後編でお届けします。(※文中敬称略)

プロフィール
【中央】岸田里佳子(きしだりかこ)
内閣官房 地域未来戦略本部事務局 審議官
1993年建設省入省。都市計画等の規制誘導、民間活用による都市再生、地域資源を活用した歴史的街並みの保全・再生、公民連携プロジェクト創出による地域活性化、防災まちづくり等の政策を推進。中央区都市整備部長、国土交通省住宅局市街地住宅整備室長、同都市局都市安全課長等を経て2025年11月より現職。趣味:家族と各地の「謎解き街歩き」に参加すること
【左】中田貴子(なかだたかこ)
集英社ブランドビジネス部 部長代理 兼 第9編集部(BAILA/non-no)部長代理
non-no、BAILA、éclatと20~50代の女性ファッション誌編集部にてファッションページを担当。2020年MOREプリント版編集長、2022年MOREブランド統括/WEB編集長、 2021年よりMORE JAPANプロジェクトを立ち上げ地方創生チームを創設。 2025年6月より現職。 趣味:ランニング・ピアノ
【右】清田恵美子(せいたえみこ)
集英社メディアビジネス部 部次長 兼 エディターズ・ラボ課 課長
1996年入社、MORE編集部にて10年にわたりヒューマンページ(インタビュー、生き方記事、食、旅など)を担当。2006年 広告部 営業第2課。2014年 美容誌MAQUIA副編集長。2021年 同・プリント版編集長。2024年よりメディアビジネス部。2025年6月よりエディターズ・ラボ課にて地方創生プロジェクトを引き継ぐ。趣味:お酒、旅
10年間の反省と認識の変化を明文化
中田 「MORE JAPAN」は、2022年に『MORE』編集部が立ち上げた地方創生プロジェクトですが、今後は「MORE JAPAN by SHUEISHA」として集英社のオールメディアで推進することになりました。『MORE』が大切にしてきた“等身大のまなざし”を活かして、地方創生の一助になれたらと考えています。
地方創生のはじまりとなる2014年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の決定から11年。2025年6月には地方創生の新たな基本構想が閣議決定されました。まずは、地方創生の新たな基本構想について、これまでとの違いからお聞かせください。
岸田 基本的な課題意識は変わっていませんが、過去10年の取り組みについての反省と、認識の変化を打ち出したことが非常に大きいのではないかと思います。まずひとつに、コロナ禍で一時的な逆流があったとはいえ東京一極集中の大きな流れが変わらない中で、若者や女性が生活圏として地方を“選ばない理由”にしっかりリーチできていなかったことを反省すべき課題として挙げています。もうひとつが人口減少への認識の変化です。人口減少に歯止めをかけたい思いに変わりはありませんが、当面避けられない事態であることを正面から受け止め、「人口が減少しても社会や経済が機能する適応策を講じていく」ことを明記しました。また「アンコンシャス・バイアス(性別や年齢、学歴などに対する無意識の思い込み・偏見)」など意識変革の必要性に触れていることも大きな変化ですし、これらを地方創生の文脈で申し上げるのは初めてのことだと思います。
中田 明文化されたことによる反響はいかがでしたか?
岸田 さまざまな選択肢や生き方がありますから、もちろん今の地方の状況を心地いいと感じる方もいらっしゃいますし、それは素晴らしいことだと思います。一方で、周囲のアンコンシャス・バイアスや、地方特有の付き合いにつらさを感じている方にとっては、こうした言葉が入ったことで非常に喜んでいただいていると感じます。具体的な実践として、魅力ある職場づくりを通じて、その地域で生き生きと暮らせる風通しのよさをつくっていくと打ち出したことも大きいのかなと思いますね。
中田 確かに風通しのよさが大事というのは、地方だけでなく日本社会全体にいえることでもあります。いきなりガラッと変わるわけではないけれど、まずは課題を認知し、意識することから生まれる変化はきっとあるでしょうね。
岸田 まさに我々もそうした課題を認知し、地方創生に取り組む上で若手や女性の職員との意見交換を行っています。
「関係人口」に着目した「ふるさと住民登録制度」の創設
清田 居住してはいないけれども、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人々を指す「関係人口」(※1)という考え方が主流になってきましたね。
※1 総務省では、関係人口を「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々」と定義(参照:総務省「関係人口」ポータルサイト)。例えば「その地域が好きで何度も行っている人」「その地域に何らかのルーツがある人」「過去に住んでいた・働いていた人」「その地域のまちづくりに参加したいと思っている人」などが関係人口にあたる。
岸田 移住に限らず地方と多様な関わり方ができるように、副業・兼業や二地域居住の推進、そして「ふるさと住民登録制度」(※2)の創設を検討中で、現在そのプラットフォームとなる専用アプリの開発に向けて動いているところです。
※2「ふるさと住民登録制度」 住居地以外の地域に継続的に関わる人が「ふるさと住民」として登録する制度。消費活動による地域経済への貢献、ボランティアや仕事を通じた地域への貢献が想定されている。
中田 どのような制度なのでしょう?
岸田 アプリを通じて、「関わりたい・応援したい」と思った地域の「ふるさと住民」に登録できる仕組みです。地域からは情報や行政サービスなどを提供し、ふるさと住民の方には二地域居住やボランティア、副業、買い物や短期間滞在などで関わっていただくイメージです。先行事例としては、ふるさと住民として何度か現地を訪れると、航空券代の「ふるさと住民割引」を受けられるサービスなどもあります。今、政府一丸となって実現に向けて取り組んでいるところです。
清田 登録している人同士で、「この地域よかったよ」と意見交換ができるとさらに広がりそうですね。ふるさと納税を活用されている方も多いですし、若い人の場合は「この地域を推したい」という“推し活”の感覚もありそうな気がします。同時に、自治体の情報の見せ方がかなり重要だと思うので、我々のような媒体がお手伝いできることはあるかもしれません。
中田 完全ローンチの前に若い世代の人たちに触れてもらってブラッシュアップできると面白そうですね。そうやって関わることで「自分たちのアプリ」という気持ちも高まる気がします。まさにアプリ自体を推したくなるのではないでしょうか。
岸田 なるほど! 担当する総務省にアイデアを伝えますね。
性別に関わりなく、多様な生き方を気軽に選択できる社会へ
中田 基本構想には、地方の「顔の見える関係性」に「多様な生き方の尊重」を組み合わせると記されています。個人的なご意見として伺えたらと思いますが、若者や女性にとって、あるいはそれ以外の人にとっても、“居心地よく、自由でいられるコミュニティ”を実現するには、どんなことが必要だと思われますか?
岸田 そうですね……今回の基本構想をまとめるために若い方々からお話を伺う中で、「仕事」にまつわるお話がとても多かったんです。「地元にやりたい仕事がない」ということもありますし、女性の場合は仕事を頑張るつもりで地元の会社に入社したけれど、お茶汲み的な業務が多い現実に直面して心が折れてしまい、都市に出ることにしたという方もいらっしゃいました。性別による固定的な役割分担ではなく、能力とやる気で仕事が進められるような機運があると暮らしやすくなるのかなと思いますね。
中田 そのためにも職場から変化して風通しをよくするということですね。
岸田 そうですね。私たちも各省横断で、希望される自治体の職場改革をサポートしています。具体的には商工会などでセミナーを開催したり、ワークショップで話し合ってみたり。非常に地道な取り組みではありますが、今までとは違う考え方や柔軟性を取り入れていくことを目指しています。
清田 これまで“当たり前”だと思っていた意識を変えていくには根気強さも必要ですね。
中田 逆に女性の側にある“女性だから仕方ない”といった刷り込みも変えていく必要があるだろうと思います。私たちメディアがその機運を盛り上げつつ、「女性たちはこういうことを求めている」という声をすくい上げて広く知っていただくことも必要かもしれませんね。
岸田 そうですね。性別に関わりなく、それぞれが多様な生き方を気軽に選択できるようになったらすごくいいなと思います。“言うは易く行うは難し”ですが、私たちもそこを頑張って目指したいなと思っています。